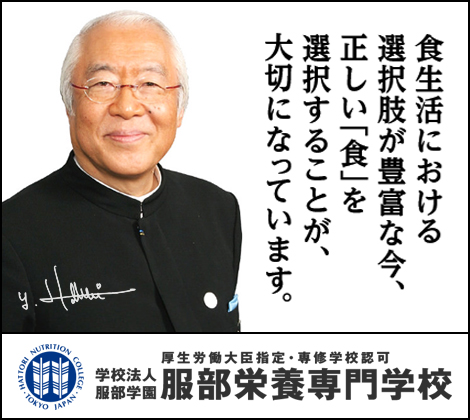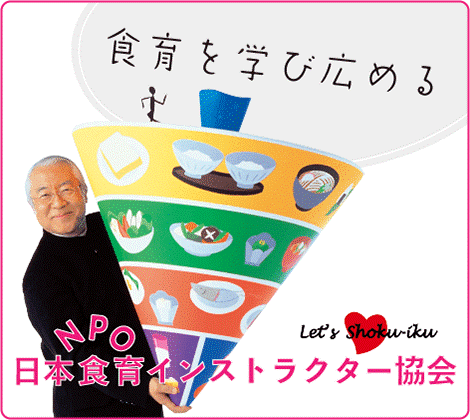2024年は日本でも、食べ物にまつわる諸問題が数多く取り上げられました。
お金を払えばいつでも必ずおいしい食べ物が手に入る、という現代のあたり前を見直す機会になったと言えます。
今回はそんな食についての考え方をより深める、食農教育についてお話します。
【食農教育とは?】
昨今は食の多様化や流通網の発達にともない、いつでも食べ物を手に入れることができる環境です。
便利な反面、消費者の食べ物への興味・関心が下がり、食べ物がどのようにして育ち、収穫され、流通を経て販売されているのかがわかりにくく、生産者とのギャップが生まれることが懸念されています。
食農教育とは、そんな状況を改善するための方法として、JAや農林水産省が中心となって進めている食への取り組みのひとつです。
日々の食を維持していくのに欠かせない存在である「農」についての理解を深める、実践的な教育の場をつくっています。
これらの取り組みは食育の三本柱にも大きく関わり、特に「選食力を養う」・「食糧問題や環境問題など、地球規模で食を考える」に影響しています。
安全な食品を選ぶことや、持続可能な食をめぐる環境について考えるためには、食べ物がどのようにして作られるかの知識をつけることで、理解が深まりやすくなります。
【食農教育、どうしたら参加できる?】
食農教育の最も一般的な取り組みのひとつが、農業体験です。
作物が育つ様子を間近で見て体験することで、「農」への理解をより深めることができます。
特に食農教育に力を入れている自治体では、生産者と協力して定期的に農業体験を開催していることもあるので、通いやすいものがないか探してみるとよいでしょう。
また、自分でも家庭菜園を行うと、植え付けから収穫までのプロセスをすべて体験できるので、食農教育の中でも特にチャレンジしてみたい内容です。
リボベジや室内で栽培できる簡単なものから少しずつスタートしてみましょう。
そのほか、ファーマーズマーケットの利用を積極的に行うことも、食農教育のひとつになります。
地域でどんな作物が育てられ、収穫時期がいつなのかの知識を深めるとともに、地産地消の概念も自然と身につけやすくなります。
こちらは普段の買い物などで利用することができ、特別にスケジュールをあけなくてもよいのがメリットです。
実際に収穫した作物をどのように調理すればおいしく安全に食べられるのかを学ぶことも、食農教育のひとつです。
親子料理教室などはさまざまな自治体で行われているので、家族で参加して一緒に学ぶことで、楽しみながら食品への関心を高めることができます。
食農教育は教科のようにこれと決まった内容を学ぶのではなく、日常生活で体験することができるものです。
自治体によっては保育園・小学校などでの食農教育に力を入れている場合もありますが、そうでない場合は自分から積極的に行動してに「農」の体験をしてみてはいかがでしょう?
簡単なものなら買い物ついでに行えるので、それほどハードルが高いものではありません。
これからの日本の食をめぐる問題への改善・解決のためにも、ぜひ食農教育について考えていきたいですね。
Text by はむこ/食育インストラクター