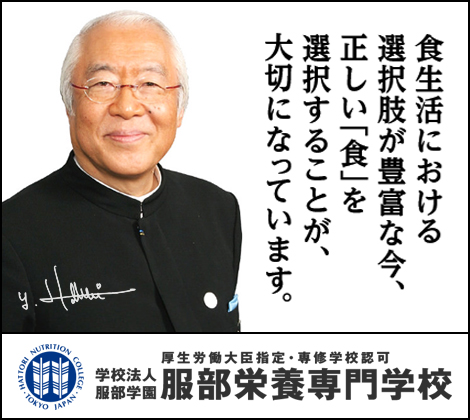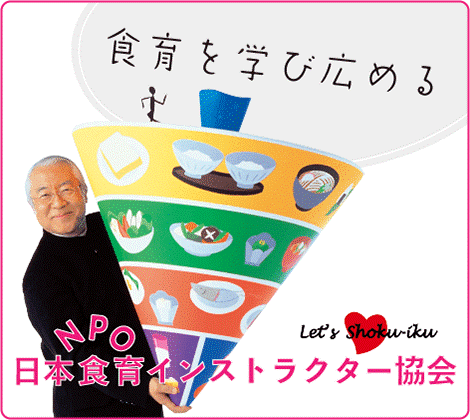代表的なお酒のおつまみで、大人から子どもまで多くの人に人気の枝豆。
今回はそんないつも何気なく食べている枝豆についてのお話です。
【そもそも枝豆って?】
枝豆は、大豆の未成熟な豆のことを指し、完熟すると「大豆」になるんです。
つまり、大豆が未熟な緑色の状態で収穫したものが枝豆です。
枝豆という野菜があると思いがちですが、その正体が大豆だなんて驚きですよね。
また、枝豆には多くの品種があり、その数はなんと400種類以上です。それらは大きく3つの種類に分けられます。
●青豆
一般的な鮮やかな緑色の枝豆です。
サヤの産毛が白いものが多く「白毛豆」とも呼ばれています。
関東地方をはじめ日本全国で栽培されています。
●茶豆
一般の枝豆は関東地方の生産が多いのに対し、茶豆は東北地方で多く栽培されています。
外見は普通の枝豆ですが、サヤの中の豆が茶色の薄皮に包まれていることから茶豆と呼ばれています。
甘みが強く独特の風味があるのが特徴です。
山形県の「だだちゃ豆」や新潟県の「黒埼茶豆」が有名です。
●黒豆
おせち料理などで使われる黒豆を成熟しきる前に収穫したものが「黒枝豆」です。
豆がうっすらと黒い薄皮に包まれているのが特徴で、関西地方で多く栽培されています。
兵庫県、京都府、岡山県、滋賀県などで栽培されている「丹波黒枝豆」が有名です。
【おいしい枝豆の選び方とゆで方】
枝豆を購入するときは、豆がしっかり詰まっていて産毛が多く、緑色が鮮やかなものを選びましょう。
また、枝豆をゆでるときに大切なのは塩の量です。
塩はゆでる水に対して4%の塩加減くらいが望ましいです。
ゆでる前の下ごしらえとして、サッと洗った枝豆のサヤの両端部分をハサミで少し切り落とします。
こうすることで、ゆでたときに塩味が豆にいきわたりやすくなります。
4%の塩の半分を枝豆にかけ、強くゴシゴシと塩もみします。
この作業のおかげで、産毛を取ることができます。
次に、鍋に水を入れて沸かし、残りの塩を入れて沸騰させます。
沸いたら塩がついたままの枝豆を入れます。
再沸騰したら、火を少し弱め3~5分ゆでて枝豆に火を通します。
そのあと、ザルにあげて手早く冷まします。
流水で冷ますと風味が逃げてしまうので注意しましょう。
【枝豆の保存方法】
枝豆は鮮度が落ちやすい食材です。
冷凍や冷蔵で保存できますが、買ったその日か翌日までに食べるのが一番おいしく食べられます。
食べきらない場合は、生のまま冷凍保存がおすすめです。
水洗いし、キッチンペーパなどで水気をしっかり拭き取ります。
そして、できるだけ枝豆が平らになるように保存袋に入れて冷凍します。
使う分ごとに分けて冷凍しておくと袋ごと解凍できるのでおすすめです。
召し上がる際は、凍ったままサヤの両端をはさみで切り落とし、塩ゆでしてください。
また、冷蔵する場合は塩ゆでし、完全に冷ましてから保存しましょう。
【気になる枝豆の栄養】
●たんぱく質
枝豆にはたんぱく質が豊富に含まれています。
たんぱく質は、身体の筋肉や臓器を構成する栄養素です。
ホルモンや酵素の材料にもなるので、病気と戦う免疫抗体にもなります。
●イソフラボン
枝豆は未成熟の大豆であるため、ポリフェノールの一種である大豆イソフラボンが含まれています。
イソフラボンは、女性ホルモンのバランスを整える働きがあり、更年期障害の改善や骨粗しょう症の緩和、乳がんの予防などに効果が期待できます。
いかがでしたか?
枝豆はゆでて実をそのまま食べる以外にも、ご飯や和え物、ポタージュなどさまざまな使い方があります。
ぜひ楽しんでみて下さいね。
Text by あお/食育インストラクター