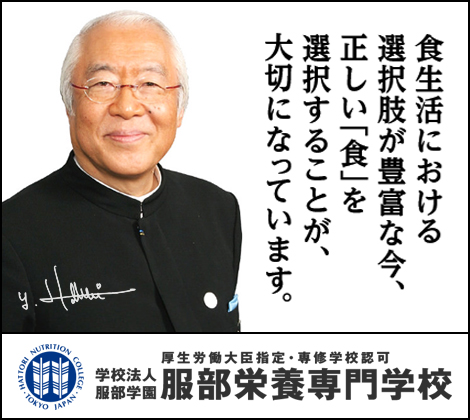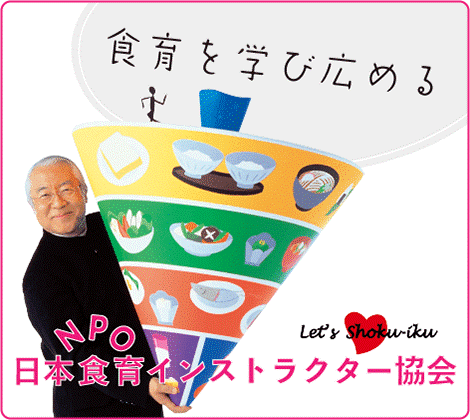乾燥の状態で売られている「ひじき」は、一年中手に入りやすいので常備している人も多いのでは?
栄養価が高く、嬉しい効果がいっぱいのひじき。
その効果やひじきの煮物を使ったかんたんアレンジレシピをご紹介します。
【昔から食べられていた海藻「ひじき」】
ひじきは縄文時代から食べられていたと言われるほど、古くからある食材です。
奈良時代の文献には、「鹿尾菜」という漢字で登場しています。
これは、見た目が鹿の黒くて短い尻尾に似ていることから、この字があてられたと言われています。
当時、ひじきは神へのお供えもの「神饌(しんせん)」として用いられており、庶民が食べるようになったのは、江戸時代に入ってからのようです。
【ひじきの加工工程】
ひじきは、北海道から九州までの太平洋沿岸と福井県以西の日本海沿岸に生息する、褐藻類ホンダワラ科ホンダワラ属の海産物です。
国内の産地は、長崎県、三重県、千葉県などが有名ですが、国産の流通量は1割ほど。
ほとんどが韓国や中国からの輸入でまかなわれています。
ひじきは生のままでは渋みが強いため、下記の方法で加工したものが売られています。
■蒸乾製法
乾燥した原料を水洗いしてから蒸し上げ、再度乾燥させる製法のこと。
三重県の伊勢地域で江戸時代から伝わる加工方法で、「伊勢製法」とも呼ばれています。
■煮乾製法
原料を生のまま、ゆでたり、蒸したあと、乾燥させる製法のこと。
千葉県の鴨川地域で用いられている製法で、「房州製法」とも呼ばれています。
大量に加工しやすいという点から、市場に出回る約8割は、蒸乾製法で加工されたもののようです。
【ひじきの種類】
■長ひじき
ひじきの茎の部分を乾燥させたものです。
繊維質が多く、しっかりとした歯ごたえが特徴です。
炒め物や煮物、和え物などさまざまな料理に活用できます。
ただ、水分を含みやすく、長時間加熱すると煮崩れしやすいので煮物にするときは注意が必要です。
■芽ひじき
ひじきの芽の部分を集め、乾燥させたものです。
風味、食感ともにやわらかく、食べやすいのが特徴です。
サラダやごはんなどにおすすめです。
【ひじきの選び方と戻し方】
ひじきを選ぶときには、黒々としていてツヤがあるもの、形が揃っているものを選びましょう。
水で洗ってからたっぷりの水につけ、20~30分程度おいて戻してから使います。
時間が無いときには、たっぷりの熱湯につけると、10分程度で戻ります。
【ひじきのうれしい効能】
ひじきには日本人が不足しがちな、骨や歯をつくるのに欠かせないカルシウムが豊富です。
カルシウムは体内で吸収されにくいので、吸収を助けるビタミンDやビタミンEを含む食材と一緒に食べるのがおすすめ。
ビタミンDはきのこやしらす、卵などに、ビタミンEはナッツやかぼちゃなどに多いので、ひじきの煮物に干ししいたけをプラスしたり、蒸したかぼちゃにナッツとひじきの煮物を合わせてサラダにすると、おいしく効果的にカルシウムを摂ることが出来ます。
そのほか、皮膚や粘膜を丈夫にして免疫力をアップさせるβ-カロテンやお腹の調子を整える食物繊維も含んでいます。
【ひじきの煮物があまったら・・・。「チャーハン」にリメイク!】
ひじきの料理といえば、「ひじきの煮物」が定番ですよね。
常備菜としても重宝するので、ひじきを買ったら煮物にする方も多いのでは?
でも、2~3日すると誰も手をつけず残ってしまうことも・・・。
残ったひじきの煮物をチャーハンにリメイクします。

<材料(1人分)> 調理時間:10分
ごはん・・お茶碗1杯分(約150g)
ひじきの煮物・・大さじ3程度
溶き卵・・1個分
ちりめんじゃこ・・大さじ1
長ねぎ(みじん切り)・・5cm分
塩・こしょう・・適宜
ごま油・・大さじ1/2
<作り方>
- フライパンにごま油を入れて強火で熱し、薄く煙が出てきたら溶き卵を入れてひと混ぜし、ごはんを加え手早く炒める。
- ごはんがほぐれたら、ひじきの煮物・じゃこ・長ねぎを入れて炒め合わせ、味をみて塩・こしょうで調える。
ビタミンDが多い、卵とじゃこを合わせ、カルシウムの吸収をアップ!
ひじきの煮物の味はご家庭によって違うので、入れる量は加減してください。
旬を感じにくいひじきですが、3~5月の今の時期に旬をむかえます。
味にクセがなく、さまざまなアレンジが可能なので、ぜひいろいろな料理に活用してください。
Text by まち/食育インストラクター